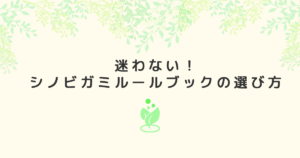SNSから離れろ! レコメンドから逃げろ!

最近、というか結構前からSNSを見る頻度を大きく下げるようにしています。
これ、あまり大真面目に解説している人が多くはないのですが、何度か聞いたことがある根拠のない話、テレビ脳、ゲーム脳、なんかと違って結構深刻な問題だなあと思ったりしています。
結論から言っちゃうと「レコメンド機能を使わない」ってことなんですが、これが超重要なんですよーというお話をしたいと思います。
元々、私自身がこういう思考を持っていたんですが、最近ゲームの解説してるYouTuberのナカイドさんって方がSNSの扱い方について言語化されてて「そうそうこれこれこれー」って思ったのでTRPG界隈の考えとかを混ぜながら自分の考えと交えて紹介したいと思います。
モンハンワイルズが低評価まつりになっているという動画ですが、もっと踏み込んでなんでSNS上で、こういうネガティブな意見が拡散されるのかその構図とかを解説されてて、めっちゃ面白かったですも。
意見を言うのは悪いことじゃない
まず最初に言いたいのは、自分の考えを持つことって別に悪いことじゃないってことです。当たり前のことなんですけどね。人間です。色んな思想や考えがあって当然ですよね。
そしてそれを誰かに発信するのも自由です。好きなものを語るのも良し、布教活動に努めるのも良し、ただ一方でポジティブな話は歓迎されますが、ネガティブな話は人から敬遠されがちだなーって感覚ありますよね。
否定意見は書くな、誰かがそれを見て傷つくかもしれないだろ、空気読め、って確かにその観点は理解できますが、ネガティブな要素も含めて意見です。良いところも悪いところも本来は忖度なく言って構いません。ネットというのはそういう場所だと私は考えます。
ところがネットではよくこの個人的な思考を「発信」することでトラブルになることが頻発している印象を受けます。一体なぜなんでしょう?
「肯定」は実は誰かを傷つける
ここで肯定的な意見も否定的な意見も、どっちも誰かの自己肯定感を上げ下げしてます。
自分の好きなコンテンツに対して肯定的な意見を見ると、気分が良くなりますよね「こいつ分かってんな」ってなるわけです。こうして同じ意見を持った人の自己肯定感が満たされます。そして自分の好きなコンテンツを咎める意見を見るとテンションが下がります。「なんだこいつムカつくー」って。
だから、あまり否定意見をネットに書くべきではないって言われるんです。ネガティブな話は必ずどこかで誰かを傷つけるからって話ですね。
ただ、実は肯定的な意見も誰かを傷つけるんです。「俺の嫌いなあれがなんで絶賛されてるんだ? 腹立つー」ってなるわけです。例えですけどカルト的な政党がめちゃくちゃ勢力を伸ばしてて爽やかに「がんばります!」って言ってるコンテンツ見ると傷つきません? イライラしません?「なんでこいつが絶賛されてるんだ?」って。
これがポジティブな要素でも人を傷つけるという仕組みです。自分の嫌いなものが絶賛されてるとイライラするんです。自分の好きなものが貶されるとイライラするんです。ここに実は差はなくて「ただの考えの相違」なんですよ。
例えば、私はTRPGシステムのCoCがめちゃくちゃ苦手です。苦手な理由としては以下の通りです(本流と関係ないので伏せておきます)
CoCが苦手な理由
TRPGの醍醐味は「キャラクターになれる、体験できる」という没入感なのに、プライヤーが考えないと進まない探索要素はそれを阻害して没入感を奪いってしまう。更に興味や関心もない神話的恐怖が世界観の中核を担っているので、世界観、ゲーム性、RPの没入感、何を取っても楽しいポイントが見つからない。
CoCのPCたちは探索者ですから、その探索が苦痛なら遊ぶ資格はないし根本的に一切向いていない。心の底から私のやりたいTRPGの要素を邪魔しかせず、探索を楽しみたいならコンシューマーゲーム遊ぶ方が100倍楽しい。
どれだけ有名で名作と言われるようなシナリオもCoCという遊びに乗せられた時点で苦行になることが分かっているので、「インセインにコンバートしてくれたら遊ぶよ」と思っているわけです。
この感想は私個人のものであり、CoCを愛好される方々の価値観を否定するものではありません。
といった具合です。こういう意見を投げることで、
- 同じように苦手な人は「わかる!私も思ってた!」って気持ちが満たされる
- CoCが好きな人は「自分の好きなものを否定された」って気分が悪くなる
となるわけです。否定意見によって誰かの自己肯定感を上下させている。
逆に、私が普段楽しんでいるシノビガミやマギカロギアを絶賛しても、
- シノビガミが好きな人は賛同意見があったことで嬉しくなる
- シノビガミが嫌いな人は「なんで絶賛してるんだ?」ってイラつく
こういうポジティブな意見でも誰かの自己肯定感を上げ下げする。上げるのはイメージ付きやすいと思いますが、ポジティブな言葉が誰かの自己肯定感を下げて傷つけているって感性は持っている人少ないですよね。でも現に、私はCoCが日本のTRPGで覇権取ってるこの構図は嫌ですもん。未だにTwitterにユーザーが多くいる現状嫌ですもん。つまり私は傷ついているんです。
これって当然のことなんです。人間だもん、好き嫌いがあって当たり前。趣味、政治、経済、あらゆるコンテンツや思想がバラバラ、嫌なものを見ると気分が悪くなる、これも当然。だから好きな意見だけを吸収して自己肯定感を高めていきます。
「人が好きなものをその人の前で否定するな」ってネットの歩き方で良く言われますよね。というかコミュニケーションの基本ですよね? 否定的な考えや意見というのは、なるべく排斥して良い声だけにした方が気分よく楽しめます。 これをエコーチェンバー現象と言ったりします。
そしてTRPG界隈はその思考がネットの平均よりも更に強いです。肯定と称賛の文化ですからね。 PLを褒め、GMを褒め、シナリオ製作者を褒め、シナリオの良い部分をいっぱいピックアップして共有するような文化圏です。 否定や批判になれていないので、CoCシナリオのレビューサイトができたときも燃えました。
一方で、何かを褒めたり称賛することが、誰かの自己肯定感を下げているということはあまりピックアップされません。個人的には肯定的な意見は認めて、否定的な意見は認めないっていう感性は正直気持ち悪いです。
自分の自己肯定感が下がるような発言は、発言を拒否するのではなく、発言を聞かなければいいんです。自分の好きなコンテンツを嫌っている人なんてフォローしなければいいんです。自分の嫌いなコンテンツなんてわざわざ見にいかなければいいんです。
絶賛しても否定しても誰かが傷付き誰かが喜ぶ。だから考えることは自由。発言するのも自由、でも誹謗中傷とかの攻撃はしないでね。私たちは見たい発言だけ見に行き、嫌な発言は見ないようにする。棲み分け大事。
ここまではいいんですよ。ところが昨今のSNSにはこの違う意見の人をマッチングさせるシステムが用意されています。この住み分けがうまくいかなくなってるんですよねえ。
「見に行く」から「見せられる」時代へ
ここ10年間で、インターネットプラットフォームは劇的な変化を遂げました。これはただの機能改善ではなく情報との関わり方自体を大きく変えました。
昔のネット(2010年代前半まで)
- YouTubeは動画を「検索」するサイト
- Twitterは「フォローしている人」の発言だけが見える
- 自分から情報を探しに行くスタイル
- 見たいものを見に行く世界
今のネット(2020年以降)
- アルゴリズムが「あなたにオススメ」を勝手に表示
- 検索してないのに関連動画が無限に出てくる
- 自分が見たくない情報まで強制的に見せられる
- 見せられる情報を受け取る世界
皆さん、こんな経験ありません?
- YouTubeのショート動画を見てたら、気づいたら1時間経ってた
- 目当ての動画を見た後、次のオススメで延々と動画巡りをしてた
- Twitterで流れてきた話題のツイートで、ネガティブな気持ちになった
私もこれが増えるようになってきて危機感を抱くようになったんですよね。
そして問題の核心:違う意見の人を強制マッチング
ここからが今回の話の核心です。今のSNSは昔だったら住み分けできてた異なる意見の人たちを、現代のSNSは強制的にマッチングさせてるんです。
プラットフォームの狙い
SNSプラットフォームは、とにかく私たちの注意を奪うことを目指してます。そこでどうするかというと、「好きなコンテンツ」ではなく「感情を動かすコンテンツ」を表示するんです。
例えば、あなたがTRPGの楽しい投稿を見てると、アルゴリズムは「この人TRPGに関心がある」って判断します。そして、TRPGの楽しい話だけじゃなく、TRPGを批判する意見や炎上ネタも混ぜて表示してくるんです。
なぜかって?感情が動いた方がタップしやすいからです。
なぜこんなことをするの?
答えは簡単。お金になるからです。
感情を高ぶらせて、ランダムな表示から脳に刺激を与えて、最終的には感情を上げ下げして揺さぶって、依存度を高めて滞在時間を増やす。これが現代SNSのビジネスモデルなんです。
「むかつくー」ってなりながら関連ツイートを追ったり、トレンドの検索ワードを見たりしちゃいますよね?それがもうプラットフォーム側の思うツボ。
本来なら出会うはずのなかった対立する意見同士を、わざと出会わせて感情を煽ってるんです。
現代のインターネットは私たちの注意力ビジネスと言われています。以下にして意識をスマートフォンの中の情報に向けさせるか、以下にユーザーに受動的に情報を受け入れさせて時間を消費させるか、それがプラットフォーム側の狙いです。
このシステムの基本構造は以下の通り
- データ収集:ユーザーの行動、感情、反応を詳細に記録
- 行動予測:機械学習アルゴリズムによる行動パターンの分析と予測
- 行動操作:予測されたパターンに基づく感情的誘導
- 収益化:滞在時間の延長と広告効果の最大化
プラットフォームが「感情を動かすコンテンツ」を優先する理由は明確です。
- 強い感情反応はエンゲージメント(いいね、コメント、シェア)を増加させる
- エンゲージメントの高いユーザーは滞在時間が長く、広告価値が高い
- 怒りや不安などの否定的感情は、肯定的感情よりも強い行動誘発効果を持つ
そのためプラットフォームは、ユーザーが不快に感じる可能性の高いコンテンツの表示。政治的・社会的対立を煽る情報の優先配信。建設的でない議論や炎上案件の拡散促進。なんかを行うわけですね。
特に今みたいな選挙前の時期だとこれが顕著になります。ちょっと意見や刺激の強い政党の支持者のツイートばかりが流れてくるのは、SNS側がインプレ稼げるものを表示させてるからなんです。
だから正しいかどうかではなく、あなたが好きかどうかではなく、とにかく刺激の強い情報をランダム的に鳴らして脳にドーパミンを流し込んでくる。
これはいわゆる陰謀論的な「SNSのプラットフォームは俺達の脳をAIで監視してるんだー」的な話がしたいわけじゃないです。AIでスマホの中身を管理しているなんか当たり前で、これは変な話じゃなくてただIT企業として科学的に脳をハックしてきているだけです。プラットフォームもビジネスなんです。
人間の脳は、こんな情報過多に対応できません。人間の脳は数万年前からほとんど進化しておらず、小さな集落での生活に最適化されてるんです。一度に4〜7項目しか処理できない脳に、現代のSNSは常にその何倍もの情報を押し付けてくる。そりゃ疲れますよね。
レコメンドから逃げてSNSを楽しもう
じゃあどうすればいいの?ってことで、私が実践してる対策を紹介します。
結論を言うと、自分の見たいコンテンツだけを積極的に見るように気をつけます。ネットを昔ながらの検索型システムとして使用し、おすすめ欄をとことん無視します。
根性論的に「俺は気にしない」「気にしないぞー」とやってもいいのですが、やっぱり効果的なのはツールを使って情報を物理的に遮断することです。
レコメンド遮断ツール
YouTube
- スマホ版では改造アプリを使って、おすすめ欄や画面内の表示情報を大幅に削減
- 動画は検索して一本見たらそれで終了、関連動画や自動再生を表示しない
- ショート動画は検索結果からも画面表示からも除外して、見たくても見られないように
YouTubeの拡張機能 – https://chromewebstore.google.com/detail/unhook-remove-youtube-rec/khncfooichmfjbepaaaebmommgaepoid
Androidの改造アプリ – https://revanced.app
Twitter/X対策
- ウェブ版では拡張機能を使って、通知欄しか見えないように
- リプライやDMには気づけるけど、タイムラインは見ない
- エゴサーチ用に専用のセッションを作って、必要な時だけ確認
Twitterの拡張機能 – https://chromewebstore.google.com/detail/kpmjjdhbcfebfjgdnpjagcndoelnidfj?utm_source=item-share-cb

これがワイのTwitterや! なんとホームすら見えない通知専用のSNSとなっています。
プラットフォームの手に乗らない意識
- レコメンドに載ってる情報をタップしない(根性論だけど大事)
- 決まったこと以外はしないルールを作る
- SNSは依存させるように設計されてることを常に意識
これらを意識することが大事です。知っていて利用するのと知らずに無駄に時間とエネルギーとお金を消費する人にはならないようにしましょう。もっと生産的な時間を使って、シナリオとかイラストとか書くのに時間使ってくださいね。
住み分けを意識的に作る
最終的には、自分の意見に合う、自分が見ていて心地よい人だけを自分のTLに固めるのがベストです。
私は苦手なシステムや苦手なシナリオについて、自分の考えを積極的に発信してます。なるべく表で言うようにすることで、私という人間を判定しやすくしてるんです。
- 「あ、このふれのって人の考え、自分に近いからフォローしよう」
- 「こいつ見てると腹立つからブロックしよう」
どっちでもいいんです! むしろブロックされることが多くなるのは、フィルタリングが進んで、私の発言を見たくない人がフィルターをかけることに成功したってことなので、「良いこと」だと思ってます。
- 苦手な人、意見が合わない人はフォローを外そう
- ミュートやブロックを積極的に活用しよう
- 私の意見が合う人は積極的にフォローしよう
- 見たくないのに意見が流れてくるなら、プラットフォームの使い方を工夫しよう
私の現在の環境
ちなみに私の現在のSNS運用は:
- Misskeyサーバー「TRPGがすき」をメイン
- そこでの投稿をTwitterとBlueskyに自動連携
Twitterは早々に見切りをつけたので今は完全に通知確認&エゴサ用になっていますが、私のツイート自体は連携機能経由で見れるようになっています。
まとめ:主体的にSNSを使おう
意見を持つのは自由、発信するのも自由。棲み分けすればよいだけです。でも本来なら住み分けできてたはずなのにレコメンドシステムが強制的に対立意見をマッチングさせて感情を煽って滞在時間を稼ごうとしてる。
なので、ツールの力を借りてSNSの情報をなるべく整理しよう。そして感情を動かされるコンテンツじゃなくて、本当に見たいコンテンツを見に行く。対立したくない人とは距離を置いて、価値観の合う人と楽しくコミュニケーションする。
そんなインターネットライフを一緒に目指しましょう! もちろん、どんどん私のこともブロック・ミュートしていただいて構いません。それが健全な住み分けってもんです。