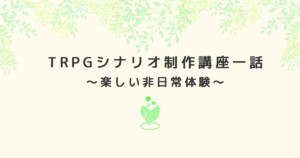TRPGにおける探索要素は没入感を阻害するのか?

はじめに
みなさん、こんにちは!今日は「TRPGにおける探索要素と没入感」というテーマについて私の主観100%で考えてみたいと思います。
最初にお断りしておきますが、特定の遊び方を否定する意図はまったくありません。ゲームの楽しみ方は人それぞれです。シューターを好む人、パズルゲームを好む人、美少女キャラクターを好む人、ゾンビやクリーチャーを好む人…千差万別ですよね。TRPGでも同じです。
どうも、ゾンビTRPGプレイヤーふれのです。では、よーいスタート!
TRPGとはリッチなおままごとである
TRPGを知らない人に説明するときに「大人のおままごと」って例え話で伝えることないですか? キャラクターになりきって、関係性を演じるという奇っ怪な遊び。この私はこの「ロールプレイ」がTRPGの核心部分だと思っています。
他にもTRPGならではの魅力は沢山あるのですが、じゃあそれはスマブラと何が違うの? マリオカートと何が違うの? トランプとウノと何が違うの? ドラクエやFFとは違う? ってなったときにTRPGならではの特色はロールプレイに集約されていると考えてるというわけですね。
逆にそこを突き詰めないと、他のコンテンツの劣化版になるとも考えています。ロールプレイ無しで展開するTRPGを遊ぶなら同じストーリーを映画で見たいです。ゲームでプレイしたいです。という考えの持ち主なのです。
台詞ではない行動宣言
「〇〇をします」「〇〇のような行動を行います」という台詞ではない行動内容を示す発言があります。
探索系ゲームにあるような行動宣言をずっと続けてマップの各地を探索するような要素は、おままごとには基本的にありません。
子どものおままごとでも「お茶を入れますね」といった行動宣言はするものです。でも、「この部屋の壁を調べます」「床下を探索します」なんて言いながら隅々まで探し回ることはないですよね。
こういった探索要素が入ってくると、「おままごとを抜け出して唐突に始まる別ゲー」となってしまうと私は感じてしまうのです。
私はTRPGの魅力は、キャラクターの視点で物語を体験できることだと考えています。基本的には会話を主体にしてロールプレイを展開したいというわけですね。あくまでも私主体の考えであるというのが前提であることをお忘れなく。
没入感が途切れる探索要素
一般的な考え方がプレイヤー=キャラクターではないことは理解していますが、私は如何にキャラクターとプレイヤーをシンクロさせるかを重要視しています。その方が物語の登場人物として没入感が得られるのです。
そうやってキャラクターの思考や感情を仮想体験している途中で、メタ的な発言があると没入感が薄れてしまいます。
探索型ゲームは、明示的に没入感を解いて、プレイヤーがゲームプレイを強要されてしまう側面があります。どこへ移動するか、どこを調べるか、それらを宣言しないと探索が進みません。
それをロールプレイと切り離して楽しめるなら良いのですが、私は切り離せず、「せっかくおままごとを楽しんでいたのに急に引き剝がされてつまらない作業を要求された」という感覚になってしまうんですよね。
しかも、厄介なことに私はせっかちな性格で、すぐに結論を求めてしまいがちです。そのため、緻密に情報を積み上げて真実を追及するような探索要素や、プレイヤーの思考と推理で真実を見つけ出すような謎解き要素、推理要素が苦手なんです。
10秒考えて分からないなら「いいから答えを教えてくれ」となる性格なんです。圧倒的に探索と謎解きに向いていない。それらをやるならコンシューマーでやった方が楽しいと考えちゃいます。
つまりCoC、エモクロアなどの探索系システムは私とかなり相性が悪いです。どれだけ良いシナリオも探索する場面になった途端にTRPGに求めている没入感から引き離されてしまいますから。。。
逆にシノビガミやインセイン、マギカロギアのようなシーン制システムはキャラの台詞と感情表現だけに集中できます。しかも判定の特技すらプレイヤーの自由です。ロールプレイを阻害するものは何もありません。
待てーい、シノビガミの戦闘は没入感を削ぐぞ?
ここで疑問が生じますよね。シノビガミやマギカロギアの戦闘シーンは、どう考えてもキャラクターの台詞や思考だけでは成立しない場面です。
先程の話をトータルすると、私はシノビガミやマギカロギアの戦闘シーンで探索要素と同じ苦痛感を味わすことになります。お前さっきシノビガミ好きって言ってたよな。二枚舌かおぉい。
と、これは確かにそうなんです。でも不思議と私はこれを楽しめています。その理由について考察してみましょう。
純粋にゲームとして面白い
シノビガミの戦闘って、プロットの読み合い、リソースの管理、一つ一つの判定のランダム要素に対するひりつき感……これらが間延びせず、楽しい体験が濃密に詰まっています。
探索パートと同じく「おままごとから別ゲーへ」という切り替えなんですが、その「別ゲー」が超絶面白いから許せちゃうんです。
マギカロギアも同様です。ゲーム性がめちゃくちゃおもしろい。逆にインセインはゲーム性が大雑把すぎて戦闘シーンは少し苦手気味です。ダブルクロスは……まだ慣れてなくて全力で楽しむところまで到達できていないかもしれません。
戦闘シーンをキャラ表現の場としている
実は私は凝った構成をあまり作らず、シンプルなキャラ構成が多いです。データ派のイメージがある方は残念でしたー。私はめちゃくちゃ構成オンチのデータ弱者です!
戦闘中もキャラへの没入感を切らさないようにして、メインはキャラクターの思考や感情であり、戦闘に対するプレイヤーとしての思考は二の次三の次だからです。
そのため、戦闘中もロールプレイをたくさんしますし、戦略面で思考を巡らせることはほとんどありません(10秒悩めば長考です)。
シノビガミの正しい裁定とかも全然気にしません。裁定考えるのに5秒時間使うならロールプレイに使います。そういうタイプというわけです。
戦闘と没入感のあるロールプレイの両立は可能です。むしろ、戦闘シーンこそキャラクターの本質が最も表れる場面だと捉えています。回想シーンや奥義描写などはその代表といえるでしょう。
ただ、それはシステムがロールプレイを阻害しない設計になっていることが条件です。
それぞれのTRPGを遊ぶ上でのウェイトをどこに置くか
TRPGの遊び方は本当に多様で、それぞれのプレイヤーが重視するポイントも異なります。ここで少し、TRPGにおける様々な「楽しさのウェイト」について考えてみましょう。
プレイスタイルの多様性
TRPGの楽しみ方を分類すると以下のような軸で分けられるでしょう。
- ロールプレイ重視型:キャラクターになりきることを最優先し、感情や関係性を深く表現することに喜びを感じるタイプ。私はこちらです。
- ストーリー重視型:物語の展開や結末に興味があり、その過程で起こる出来事やドラマ性を楽しむタイプ。一歩引いた視点でどんな結末になるのか、どんな展開が待っているのかというワクワク感を大切にする。
- 探索・謎解き重視型:情報を集め、謎を解き明かしていくプロセスを楽しむタイプ。真相に迫っていく過程でのプレイヤーの思考や推理が醍醐味です。CoCやエモクロアの醍醐味はここにあるのかも。
- バトル・ゲーム性重視型:システムのルールを使いこなし、戦略的に勝利することを楽しむタイプ。プレイヤーの判断力や戦略思考が問われる場面で楽しさを見いだせる。
- 世界観没入型:システムやルールよりも、その世界に存在することを楽しむタイプ。詳細な設定やリアリティある描写に惹かれます。
これらのプレイスタイルの好みによって、相性の良いシステムも変わってきます。例えば一例ですが
- シノビガミ、マギカロギア:ロールプレイとバトルのバランスが良く、短時間で濃密な体験ができる
- CoC、エモクロア:探索・謎解きを中心に、恐怖体験を共有できる
- ソード・ワールド:冒険とバトルを通じて戦略性やキャラクターの成長を楽しめる
- ダブルクロス:超能力バトルとドラマ性を両立。複雑なデータを理解しコンボや演出を楽しむ
- ネクロニカ:独特の世界観と物語性を重視している
私の場合、キャラへの没入感、感情、映画のような体験やドラマ性を求めています。逆にそこから引き剥がされるパートが苦手で、特に細かい探索や推理は苦行だと感じてしまいます。
ただし、駆け引きが熱いゲーム性の深いシステム(シノビガミやマギカロギアの戦闘)などは楽しめます。これはゲーム部分の質が高く、没入感を損なわない形で設計されているからなのかもしれませんね。