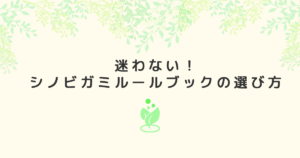TRPGの立ち絵は本当に「必要ない」?

はじめに
TRPGにおいてよく学級会で上がる論争の一つに立ち絵問題があります。
- みんな描いてるのにAさんだけ描いてない
- この人だけpixiv立ち絵で少し浮いてる
- AI生成の立ち絵を使ってほしくない
などなど、大雑把に言うとセッション時の立ち絵についての拘りみたいなものですね。
その一方で「TRPGを遊ぶのに立ち絵なんて必要ない」という論調もあります。この辺の感性は人によって違うというのを大前提に置きつつも、本当に立ち絵は描かないと、もしくは拘らないと駄目なのか? 立ち絵なんて必要ないというのは本当か? という部分にピックアップして一つ記事を書きたいと思います。
どーも、絵は描けないが、まだ10月でも大量に汗はかくふれのです。ではよーいスタート。
立ち絵文化の現状と対立構造
TRPG界隈において、時折話題に上がる学級会ネタに「TRPGに立ち絵は必要かどうか」という論争があります。
現在は、自分で何かしらの立ち絵を用意してセッションに挑むユーザーが殆どであり、SNSにその描かれたキャラのイラストやココフォリアのキャプチャーなどが流れてくることはよくあります。
立ち絵の入手方法も多様化し、自分でイラストを描く、フリーの立ち絵を使う、使用許可がされているpixivの立ち絵、AI生成の立ち絵を使う、誰かに依頼して描いてもらうなど、様々な選択肢があります。
もはやTRPGと立ち絵文化というのは切っても切り離せない関係にあります。
そんな中で絵が描ける人たちの一部から「一緒にTRPGを遊ぶなら、他の人も立ち絵を描いてほしい」「相方の立ち絵がpixiv立ち絵だとモヤッとする」「フリーの立ち絵を使わないでほしい」といった意見もあります。
それに対するアンサーとして「TRPGを遊ぶのに立ち絵なんて必要ない」「立ち絵の有無はTRPGの楽しさには関係ない」といった意見が返されることが多いです。
先に結論を言ってしまうと、こういった学級会の結論はすべて「一緒に遊ぶメンバー間のすり合わせ」です。価値観が合わないなら、そういった人との同卓は控えた方がお互いのためでしょう。
ただ、ここで思考停止せずに、なぜ立ち絵があった方が良いのか、なぜ立ち絵はなくても問題ないのか、その両方の側面からしっかり深掘りしてみましょう。
「立ち絵が要らない」は嘘
ゲームに凝ったグラフィックは不要
立ち絵なんて無くてもTRPGは遊べるし、ゲーム性に影響はしないという意見をよく聞きます。
これは確かにこの通りで、イラストがあろうがなかろうがステータスに変化はないですし、ゲーム進行的に有利不利が発生することもありません。元々のTRPGは紙とペンで出来ていたテーブルを囲む遊びでした。
それこそがTRPGの「T(テーブル)」の部分になるわけですが、その時代に今のような立ち絵を描く文化があったかと言われると否でしょう。紙にイラストは書くことはあったかもしれませんが、今とは大きく形式が違っていたと思われます(予想ですが)
コンシューマーゲームの界隈でも「ゲームに美麗なグラフィックは不要」と言われることがありますが、まさにこれと一緒です。昔のドット絵のゲームでも面白いものはめちゃくちゃ面白いですよね。
ところが、この意見は間違いだと思います。関係ないわけがない。
人間の認知特性から考える
人間というのは五感で受けた刺激から、楽しさや快楽を摂取します。グラフィックなんて必要ないって人も、悪いよりは良い景色の方がいいはずです。綺麗なグラフィックの方が楽しいのは間違いないはずです。
以下の立ち絵を想像してみてください:
- 描き込んだオリジナルの立ち絵
- 20分で描いたラフスケッチ
- pixivのよく見る立ち絵
- フリーの立ち絵
- AI生成された立ち絵
- いらすとやの立ち絵
- 実写の立ち絵
これらを見たときに全部に対して同じ感想となることは有り得ません。立ち絵はあった方がいいですし、それにオリジナリティがあった方がなお良い。へのへのもへじよりは書き込んだイラストがいい。AIよりは手書きがいい。それはもう間違いないです。
BGMやSEによる演出についても同じことが言えます。「必要ない」は嘘なんです。正確には「なくてもゲームは成立するが、あった方がいい」なんですよ。
「嫌だ」「許せる」「普通」「嬉しい」のライン
ただ、ここで重要なのは人によって求めるクオリティが違うということです。例えば人によって「嬉しい」になったり「許せない」というラインがあります。上手いイラストには加点が入るものだとしましょう。そしてどう考えても品質が至らないものは減点対象になります。
そして、「何点以上なら許せるか」と「何点から上は求めていない」が人によってまちまちです。そして当然加点や減点の対象もバラバラです。
立ち絵にしろ、ゲームのグラフィックにしろ、BGMやSEを交えた演出にしろ、ないよりはあった方が良いけど、どのくらいのクオリティが必要かがその人によって変わるというわけです。
- 求める点数(どのくらいの点数があれば「嫌だ」を回避できるか、「嬉しい」になるか)
- 加点、減点の要素(何を求めているのか)
例えば、既に90点のクオリティがあって大満足しているところに「95点に引き上げるために労力が3倍かかりました。なので価格も3倍ね?」と言われても納得いかないでしょう。実際に、90点が95点になっても気が付かない人もいます。分からない間違い探しに高コストは払いたくないものです。私もフレームレートの30fpsと60fpsの違いを見分けるのが苦手なくらいです。
でも、あまりにも低品質なものは明らかにテンションが下がります。最低でも50点はないと気になってしまうといった許容できない最低ラインがその人の中にはあるわけです。私もフレームレートが15fpsくらいになると「うわぁ」って気持ちになってしまうわけです。
立ち絵の具体的な話でいうと、私もセッションで実写形式の立ち絵使用を打診されたとき「世界観を阻害し、セッションの没入感を奪いかねない」として立ち絵使用にNGを出したことがあります。私の中では実写のその立ち絵は30点ほどの品質だったのでしょう。
ふれの基準
50〜90点が望ましい。50以下だと低品質が許せなくなり、90以上は品質があがってもそこまで劇的な変化がない
この基準が人それぞれに存在するのです。TRPGの立ち絵でも同じことが起きています。「ないよりはあった方が面白い」のは確定として、立ち絵に求めるクオリティ、許容できる最低ライン、これ以上は要らないという天井が人によって異なるのです。
立ち絵に求められる「オリジナリティ」
ただのクオリティを超えた価値
「一緒にTRPGを遊ぶなら、他の人も立ち絵を描いてほしい」という意見を改めて考えてみましょう。
先ほどの話を踏まえると、こういった方々はTRPGの立ち絵に対してそれなりに高い足切りラインを持っています。この人たちが求めているのは「他の人も立ち絵を描いてほしい」ではなく、「他の人にも(工数〇時間ほどをかけた70点以上の)立ち絵を用意してほしい」と思っているのです。へのへのもへじの立ち絵出したら怒るはずです。
ただ、ここにはもう一つ重要な要素があります。それがオリジナリティです。
立ち絵を描いてほしいという主張の根幹には、オリジナリティを重視したいという思考があります。そのキャラクターだけの個性や世界観、設定が反映されやすく、没入感や所有感が深まります。いわゆる「うちの子」「よその子」という目で愛着を持つのもオリジナリティがあることで発揮されるのです。
フリー立ち絵は没入感を削ぐ?
フリーの立ち絵、pixivの立ち絵などは、他のプレイヤーや別のシナリオのNPCなど様々な箇所で被ることがあります。別のシナリオで悪役だったNPCの立ち絵を、味方となる相方のプレイヤーが使っていた場合、どれだけ切り離そうとしても以前の悪役NPCがチラついてしまうでしょう。これは没入感を阻害してしまいます。
フリーのイラストは性質上いろんな箇所で見かけることになり、それゆえにオリジナリティが薄れ、そのキャラクターらしさや独自性が薄れた「量産型」になってしまうことを嫌うというわけです。
これはAI立ち絵にも同じような問題があります(今回は著作権的な話とかは一旦除外して考えます)。
創作コミュニケーションという観点
従来の立ち絵制作には、単なる成果物以上の価値がありました。キャラクター設定を深く考え、他プレイヤーとの創作的なコミュニケーションを促進する効果です。
拙い自作イラストが綺麗なAI立ち絵より高く評価されるのは、創作プロセスでの人間的な努力と感情投入が評価されているからです。「下手でも一生懸命描いた」という事実が、コミュニケーションの起点となるのです。
もちろん、それでも特定の点数に至らないと足切りされて不快感を示される可能性はあります。AI立ち絵を使った時点でマイナス100点という方もいるでしょうし、人の求めるクオリティラインと採点要素は結局その人次第なのです。
立ち絵はドレスコード
私は立ち絵をドレスコードだと思っています。
それなりに格式が高いお店に入るなら服装も気を配るべきですし、身だしなみも気を付けたいです。カジュアルなお店であれば、それ相応の服装で問題ないでしょう。そのお店がどれほどの格式なのか、どのくらいの清潔感や服装が求められるのかによって着ていく服装も考えるべきですし、たとえ牛丼チェーン店でもマクドナルドでもパンツ一丁で行くことはないと思います。
TRPGも同様です。シナリオやメンバーによって求められる格式が変化します。適切な立ち絵を用意することで、セッションの没入感を阻害せず、同じ温度感で楽しめるというわけです。
重要なのは、参加者全員が同じ格式認識を持つことです。カジュアルなセッションでいらすとや立ち絵を使うのは問題ありませんが、高い没入感を求めるセッションに同じ立ち絵で参加すれば、他参加者との温度差が生まれてしまうでしょう。
立ち絵はある方がいいが、それに対する姿勢はすり合わせ
この記事のまとめ
立ち絵論争の本質は「必要か不必要か」ではなく、「どの程度のクオリティやオリジナリティを求めるかの個人差」にあります。そして、その差を理解し合うことが重要なのです。
「立ち絵不要論」は間違いです。視覚的要素は確実にTRPG体験を向上させます。しかし、求めるクオリティレベルは人それぞれ。だからこそ、事前のすり合わせが不可欠なのです。
最終的に大切なこと
立ち絵は手段であり、目的ではありません。真の目的は「全員が楽しめるTRPGセッション」を創ることです。
立ち絵論争に正解はありませんが、お互いを理解し配慮し合うことで、誰もが参加しやすく、心から楽しめるTRPG文化を育てていけるはずです。一度立ち止まって冷静に自分の界隈やTwitterの学級会を見るときに立ち止まって考えてみてください。
大切なのは立ち絵のクオリティではなく、みんなで作り上げる物語の品質。そして、みんなで過ごす楽しい時間です。
まあ、ぶっちゃけ立ち絵云々だけでなくRPの品質や方向性でも求めるクオリティやオリジナリティ、そして加点減点の要素は含まれます。ならばまずは自分の許せる範囲を整理して確認してみるのも良いかもしれませんよ。